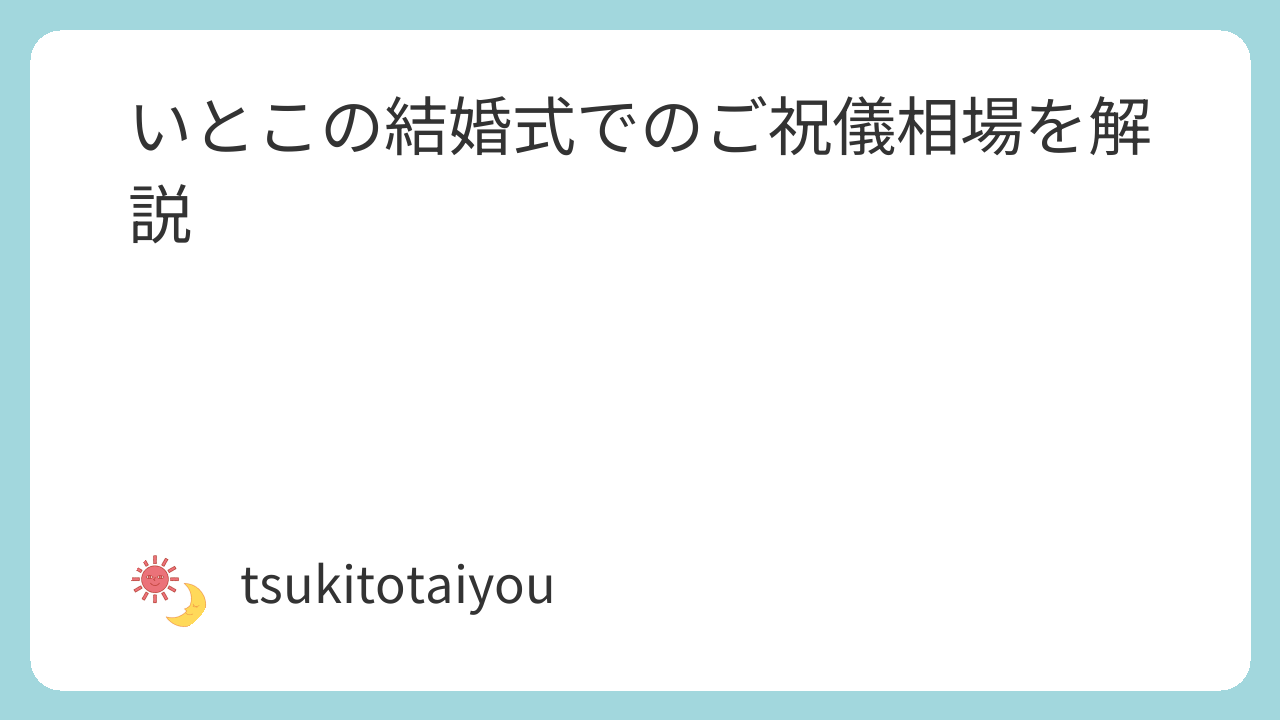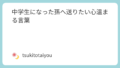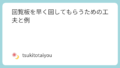いとこの結婚式に招待されたとき、真っ先に悩むのが「ご祝儀の金額はいくらにすべきか」という点ではないでしょうか。親族という立場上、あまりに少なすぎても失礼にあたると心配になりますし、逆に多すぎると相手に気を使わせてしまう可能性もあります。いとこといっても、その関係性は人それぞれで、幼い頃から頻繁に会っていた仲の良いいとこもいれば、冠婚葬祭でしか顔を合わせない程度の関係の方もいるでしょう。
そのため、ご祝儀の金額を一律で決めるのは難しく、出席する立場や状況によって柔軟に考える必要があります。さらに、出席者が独身か夫婦か、子供連れかによっても相場は変わる傾向があります。また、地域によってもご祝儀の文化や常識が微妙に異なる場合があるため、世間一般の相場を参考にしながら、失礼のないように対応したいところです。
本記事では、いとことの関係性や出席形態に応じた適切なご祝儀の金額、地域性やマナーに加えて、ご祝儀の準備やマナー、欠席時の対応までを具体例を交えて詳しく解説していきます。
いとこの結婚式ご祝儀の相場とは

いとことの関係性による相場の違い
いとことの距離感や付き合いの深さは家庭や個人によって大きく異なります。一般的には3万円程度が妥当とされており、これはあくまでも平均的な目安です。ただし、昔から家族ぐるみの付き合いがあったり、頻繁に交流していた場合、より高額なご祝儀を用意することもあります。
たとえば、特にお世話になった経験がある、あるいは兄弟姉妹のような存在だったいとこに対しては、5万円程度を包むのが心情的にも適していると考えられます。逆に、交流があまりなかったいとこであっても、親族である以上、あまりに少ない金額では失礼と受け取られる可能性があるため、最低でも2万円以上が無難でしょう。
独身、夫婦、子供連れのご祝儀金額
・独身で出席:3万円が基本となりますが、学生や新社会人など経済的に余裕がない場合は2万円でも構いません。ただし、その場合は奇数になるよう1万円札1枚と5千円札2枚に分けるなどの工夫をすると良いでしょう。
・夫婦で出席:5万円~7万円程度が一般的な目安です。親族という立場を考慮し、最低でも5万円以上を用意するのが礼儀とされています。夫婦ともに新郎新婦と関わりがある場合は、金額をやや多めに設定するのが好ましいです。
・子供連れで出席:子供の人数や年齢によって上乗せ額を調整しましょう。小学生以下で席が用意されている場合には、1万円程度を追加するのが一般的です。子供が複数いる場合は、それぞれについて同様に加算することを検討してください。
親族としての考慮点
親族という立場は、友人や同僚など一般のゲストとは異なる位置づけとなります。そのため、ご祝儀の金額もやや高めに設定されることが通例です。さらに、親や兄弟姉妹など他の親族と金額の整合性を取ることも重要になります。
親から「うちは○万円出すから、あなたも同じくらいにしておいてね」と言われることもあるため、事前に家族間で相談しておくとトラブルを防げます。また、家同士の付き合いや地元の風習にも配慮して、礼を尽くす姿勢が求められます。
一般的なご祝儀の金額目安
年代別のご祝儀金額の参考
・20代:2万円~3万円が目安ですが、学生や新社会人など経済的にまだ安定していない場合は、2万円でも失礼にはあたりません。ただし、相手との関係性が深かったり、特別な思い入れがある場合は、3万円を選ぶことで誠意を示すことができます。
・30代以降:3万円~5万円が一般的な相場ですが、社会的地位や収入の状況に応じて5万円以上を包むケースもあります。たとえば、会社の管理職や役職に就いている人は、親族としての立場にふさわしい額を意識することが求められます。また、自身が既婚で子どもがいる場合は、家族代表としての意味合いも込めて、やや多めの金額にする配慮も大切です。
このように、年齢が上がるにつれて社会的責任や経済力も増していくため、ご祝儀の金額もそれに比例して上げることが望まれます。
地域による相場の違い
地域によってご祝儀の相場には大きな差があります。首都圏や都市部では3万円が標準とされることが多く、これは物価や挙式の費用が高いことも関係しています。一方、地方では2万円~3万円が一般的とされており、地域の慣習や親族間の暗黙の了解に基づくケースもあります。
また、東日本と西日本でも相場観が異なることがあり、西日本では親族の付き合いが濃いためやや高額になることもあります。地域差に敏感になり、事前に親族や周囲の人に確認するのも一つの方法です。
具体的な金額例(1万円、3万円など)
・1万円:ご祝儀としては控えめな額で、基本的には欠席時に気持ちだけを表したい場合に用いられます。また、学生や経済的事情がある人がお祝いの気持ちを伝えるための最低限の金額としても使われます。
・3万円:最もスタンダードな金額で、独身の社会人が出席する場合に広く使われています。奇数であることから「割り切れない=縁が切れない」とされ、縁起の良い数字としても好まれます。
・5万円以上:親交が深い場合や、夫婦での連名参加、新郎新婦との関係が濃い場合に贈られます。また、家族ぐるみの付き合いがあるなど特別な事情がある場合にも、この金額が選ばれやすいです。
結婚式ご祝儀の準備マニュアル
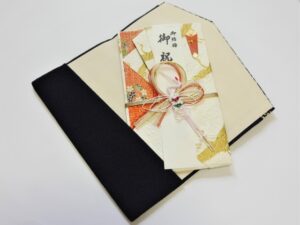
ご祝儀袋やのし紙の選び方
ご祝儀袋は、贈る金額や立場に応じて適切なものを選ぶ必要があります。水引が「結び切り」になっているものを選ぶのが基本で、「一度きりであることが望ましい」結婚のお祝いにふさわしいとされています。水引の色は紅白や金銀が一般的ですが、親族として出席する場合は、格が高いとされる「金銀結び切り」がおすすめです。
また、袋のデザインもシンプルかつ上品なものを選びましょう。表書きには「寿」や「御結婚御祝」と記し、毛筆や筆ペンで丁寧に書くことが望ましいです。ご祝儀袋の裏面には自分の氏名と住所を記入するのを忘れずに。
当日のご祝儀の手渡し方法
ご祝儀は必ず袱紗(ふくさ)に包んで持参します。受付で渡す際は、袱紗からご祝儀袋を取り出して正面を相手に向け、両手で丁寧に渡しましょう。その際、「本日は誠におめでとうございます」と丁寧な言葉を添えるのがマナーです。
袱紗の色は、慶事用として紫や赤系統のものを選ぶと安心です。ふくさを使うことで、ご祝儀袋が折れたり汚れたりするのを防ぐだけでなく、相手に対する礼儀正しさも示すことができます。
メッセージカードの書き方
ご祝儀と一緒にメッセージカードを添えると、より心のこもった贈り物になります。カードには手書きで、温かい祝福の気持ちを表現しましょう。たとえば「ご結婚おめでとうございます。お二人の未来が笑顔と幸せにあふれますように」や「末永く仲良く素敵なご家庭を築かれてください」などが定番です。形式的になりすぎず、素直な言葉でお祝いの気持ちを伝えることがポイントです。
また、できれば便せんや封筒も結婚式らしい華やかなデザインのものを選ぶと良い印象を与えます。
欠席の場合のご祝儀と気遣い
欠席の連絡とご祝儀の贈り方
やむを得ない事情で結婚式に出席できない場合は、できるだけ早めに欠席の旨を伝えるのが大人のマナーです。遅くとも招待状の返信期限前には返答を済ませるようにしましょう。口頭で伝える場合でも、改めて礼を尽くして丁寧に伝えることが大切です。
また、出席できないからといって、何も贈らないというのは避けたいところです。ご祝儀やお祝いの品は、挙式より前に新郎新婦の自宅に郵送するか、両親を通じて手渡しするのが望ましいとされています。その際には、簡単なメッセージカードを添えて、欠席を詫びつつ祝福の言葉を伝えると、心遣いがより伝わるでしょう。
代わりに贈る選択肢(カタログギフトなど)
欠席時に現金の代わりとして選ばれるのが、カタログギフトや高級タオル、食器、名入れのギフトなどです。これらは相手の好みに合わせやすく、実用性が高いため、多くの人に喜ばれます。選ぶ際は、新郎新婦の年齢やライフスタイルに合った品を意識するとよいでしょう。
また、包装紙や熨斗(のし)なども結婚祝いにふさわしい華やかなものを選ぶと、より丁寧な印象になります。贈る品の金額の目安としては、1万円~2万円程度が一般的ですが、親しい関係であれば3万円程度の品物を選んでも差し支えありません。
結婚式ご祝儀のマナー

出席時の服装とドレスコード
親族として結婚式に出席する際は、一般のゲスト以上に格式を意識した服装が求められます。男性は黒や濃紺、グレーなどの落ち着いた色合いのダークスーツが基本で、シャツは白無地、ネクタイも派手すぎないシルバーや白系が好まれます。靴も黒の革靴で統一感を出しましょう。女性は膝下丈以上のフォーマルなワンピースやドレスを選び、色はネイビー、ベージュ、パステルカラーなど上品なものがおすすめです。肩が露出するドレスの場合はボレロやストールを羽織るなどの配慮も必要です。
また、露出が多すぎたり、全身黒や白一色の服装は避けた方が良いとされています。バッグやアクセサリーも華美すぎず、結婚式の華やかな雰囲気に調和するものを選ぶようにしましょう。
新郎新婦への祝福の表現
新郎新婦と直接顔を合わせた際は、まず「ご結婚おめでとうございます」と笑顔で祝意を伝えるのが基本です。そのうえで「本当に素敵な式ですね」「末永くお幸せに」などの一言を添えると、より心のこもった印象になります。
親族同士であれば、「○○家にお迎えいただきありがとうございます」や「皆さんで楽しくお祝いできて嬉しいです」といった挨拶も場にふさわしい表現です。堅苦しくなりすぎず、しかし礼節を忘れない自然なトーンで祝福を伝えることが大切です。
お金を贈る際の注意点
ご祝儀として包むお金は、必ず銀行などで両替した新札を使用しましょう。これは「新しい門出を祝う」意味が込められているためで、シワや汚れのあるお札は失礼にあたります。
また、金額は奇数にするのが一般的で、割り切れる偶数は「縁が切れる」と連想されるため避けられます。特に「4」や「9」は「死」や「苦」を連想させるため、ご祝儀には不適切な数字とされています。どうしても偶数になってしまう場合は、1万円札と5千円札を組み合わせるなどして工夫しましょう。
夫婦としてのご祝儀相場
夫婦連名でのご祝儀の書き方
ご祝儀袋に名前を記載する際、夫婦連名で贈る場合は、まず中央に夫のフルネームを大きく書き、その左側に妻の名前をやや小さめに記載するのが一般的な形式です。名字は共通とし、夫が「山田太郎」、妻が「花子」の場合、「山田太郎」の左側に「花子」と書き添える形になります。縦書きが基本で、筆ペンや毛筆で丁寧に記入しましょう。
また、内袋に住所や金額を明記しておくと、受け取る側が管理しやすくなります。場合によっては、連名ではなく「山田家」とする書き方もありますが、正式な場面では個人名を明記した方が丁寧です。
子供連れの場合の金額設定
子供を連れて出席する場合、ご祝儀の金額設定には追加の配慮が必要です。一般的には、子供が席を利用するかどうかで追加金額が変わってきます。席や料理が用意される場合は、1人あたり5,000円~1万円を目安にご祝儀に上乗せするのが適切です。
特に、幼児でも食事や引き出物がある場合は、その分の費用負担を考慮することが大切です。逆に、乳児などで特別な配慮が不要な場合は追加しなくても失礼にはあたりませんが、念のため主催者に事前確認しておくと良いでしょう。兄弟姉妹など複数人の子供を同伴する場合は、その人数に応じて加算するのが望ましいです。
家族での出席時の注意点
家族で結婚式に出席する際には、あらかじめ主催者側に人数を伝えることが非常に重要です。大人2人に加え子供がいる場合は、子供の年齢や人数を正確に伝え、座席や料理の有無を確認しておきましょう。特に幼児用の椅子やキッズメニューが必要な場合は、早めの調整が求められます。
また、式場によっては子供用の設備が整っていないこともあるため、必要に応じてベビーカーの使用や授乳スペースの有無も確認しておくと安心です。さらに、子供がぐずったり騒いだりしたときのために、おもちゃや静かに遊べる絵本などを持参すると、周囲への配慮にもなります。
ご祝儀の負担感を軽減する方法
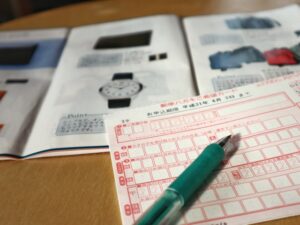
共同で贈る場合のメリット
ご祝儀を共同で贈る方法は、特に兄弟姉妹など親しい親族間で非常に有効です。たとえば、3人兄弟であれば1人あたり1万円ずつ出し合って、合計3万円のご祝儀を贈ることで、金額のバランスも取れ、見栄えのする金額になります。さらに、連名にすることでご祝儀袋の見た目も格式が保たれ、「家族一同で祝福している」という一体感も伝わります。負担を分担できるため、収入や状況に差がある場合でも無理のない範囲で誠意を示すことができるのが魅力です。
また、兄弟姉妹だけでなく、いとこ同士や親戚間での連名も可能で、親族として一丸となった印象を演出できます。金額や贈り方については、事前に話し合って合意を取っておくとトラブルも避けられます。
ご祝儀の額面を調整する方法
経済的な事情やその他の出費が重なる場合、ご祝儀の金額を調整するための工夫が役立ちます。たとえば、現金に加えてカタログギフトや記念品を添えることで、トータルの贈り物としての印象を良くすることができます。これにより、見た目や気持ちの上でも充実感があり、現金のみよりも柔らかい印象を与えることができます。
また、額面を減らす場合でも、「心を込めた品を添えた」という形にすることで、金額以上の価値を感じてもらえる可能性があります。なお、手渡しでなく郵送や宅配を活用することで、形式にとらわれずに柔軟な贈り方を選ぶこともできます。贈るタイミングや方法にも注意し、失礼のないよう丁寧に対応しましょう。
トータルでの出費の計画
結婚式に出席する際は、ご祝儀以外にもさまざまな費用が発生します。たとえば、遠方での開催であれば交通費や宿泊費がかかりますし、式にふさわしい衣装やヘアセットの費用も見込まなければなりません。また、親族としての立場であれば、それなりの服装や準備が求められるため、コーディネートにも気を遣う必要があります。そのため、事前に全体の出費を洗い出して予算を立てておくことが非常に重要です。
中には家族全員で出席するケースもあり、その際は人数に応じて負担が増えるため、早めに準備を進め、必要に応じて費用を分散させる工夫も考えておきましょう。ご祝儀の額だけにとらわれず、全体の出費とのバランスを意識して無理のない範囲で計画を立てることが、心からの祝福を届けるための第一歩となります。
まとめ
いとこの結婚式におけるご祝儀は、単に金額だけでなく、その背景にある関係性や地域の風習、さらには出席する立場や人数によっても大きく異なります。一般的なマナーを理解した上で、自分の経済状況や家庭事情とも照らし合わせながら、無理のない範囲で最大限の誠意を表すことが重要です。
たとえば、親密ないとこであれば気持ちを込めて少し多めに包む、一方で遠方からの出席で交通費や宿泊費がかかる場合はトータルバランスを意識するなど、臨機応変な判断が求められます。また、服装やマナーにも配慮し、結婚式という特別な日を新郎新婦にとって忘れられない思い出にできるよう、丁寧に準備を整えることが大切です。
この記事を一つの参考に、ぜひあなた自身の状況に合わせた心温まるご祝儀の準備を進めてください。