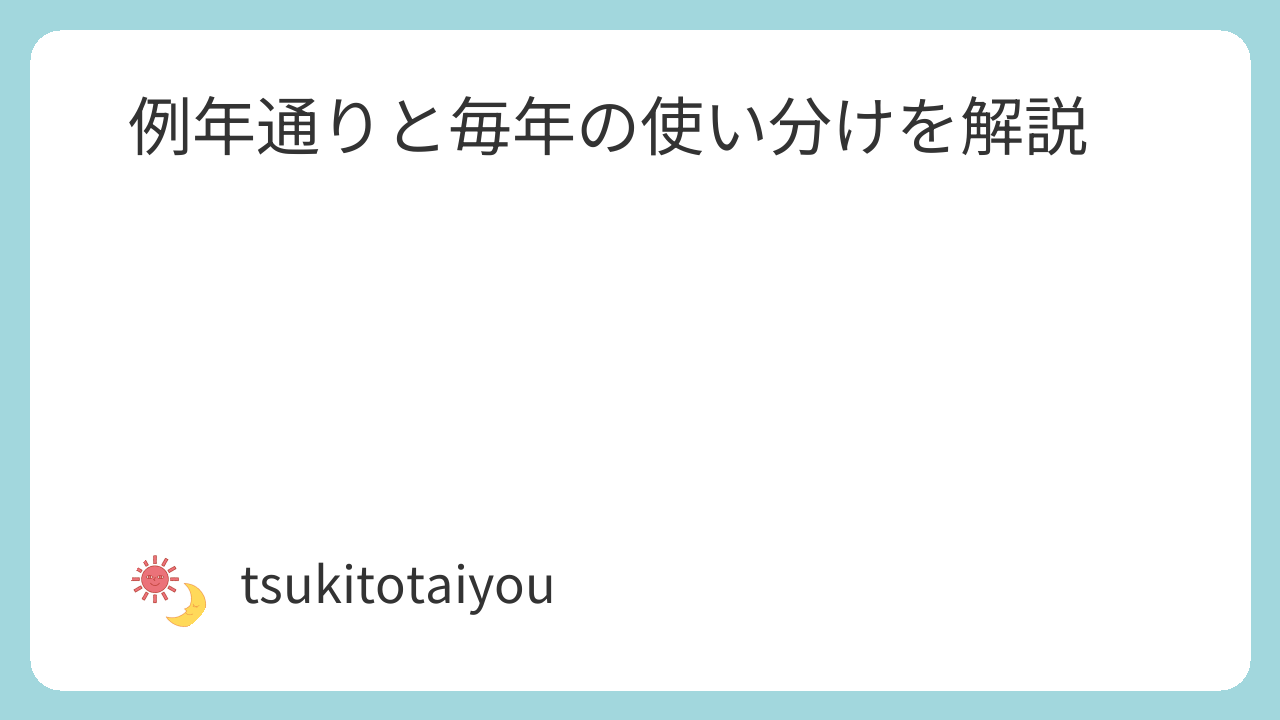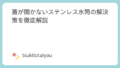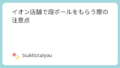「例年通り」や「毎年」といった表現は、日常のちょっとした会話からビジネスにおける正式な文書まで、さまざまな場面で頻繁に目にする言葉です。一見すると似たような意味に感じられるこれらの言葉ですが、実はそれぞれに異なるニュアンスや用途があり、適切に使い分けることで、より伝わりやすく洗練された表現が可能になります。
例えば、「例年通り」は過去の傾向や慣習を踏まえて「変わらない状態」を表すのに対し、「毎年」は単純に「毎年繰り返されること」に焦点を当てた表現です。こうした違いを理解していないと、文章の意図が誤解されたり、ビジネスの現場で意図した通りに伝わらなかったりするリスクもあります。
本記事では、「例年」の言葉の定義を明らかにすることから始め、「例年通り」と「毎年」の意味やニュアンスの違い、さらには具体的な使用例や適切な使い分けのコツ、表現を広げるための言い換えや関連語句に至るまでを丁寧に解説していきます。言葉の違いを理解し、使いこなせるようになることで、日々のコミュニケーションがより豊かで正確なものになることでしょう。
例年とは何か?

例年の意味と使い方
「例年」とは、これまでの年ごとの傾向や状況を指す言葉であり、「通常その年に起こるとされていること」や「過去の経験に基づき、毎年繰り返されると予想される出来事や状態」を意味します。この語は、過去のデータや記録、経験則に根ざした表現であり、現在の出来事を過去のパターンに照らして語るときに非常に有効です。
例えば、「例年、ゴールデンウィーク明けには新入社員の離職率が上がる」など、ある特定の時期や状況について過去の傾向に即して述べる際によく使われます。
例年とはと平年の違い
「例年」は、複数年にわたる事象や傾向を総合的に見て表現する言葉であり、「主観的な傾向」や「体感的な平均値」として用いられることが多いです。一方、「平年」は特に気象や天候の分野で用いられることが多く、気象庁や気象機関が算出した統計上の「30年間の平均値」に基づいた「客観的な基準年」を意味します。
たとえば、「平年の梅雨入りは6月8日ごろ」というように、正確なデータに裏付けされた数値で語られるのが特徴です。
例年の英語表現
英語では “usual year” や “in past years” という言い回しが使われるほか、状況によっては “typically”、”as is the case every year”、”as in previous years”、”on a yearly basis” などが表現として適しています。
例えば、「例年この地域では雪が多い」と言いたい場合には、”Typically, this region sees heavy snowfall each year.” という形で表現できます。文脈に応じて柔軟に使い分けることがポイントです。
例年通りとは何か?
例年通りの意味と使い方
「例年通り」とは、「これまでの年と同じように」「特に変化もなく慣習的に行われる状態」を意味する表現であり、過去に繰り返されてきた状況や出来事が今年もまた同じように実施される、または発生することを強調する際に使われます。この言葉は、行事や自然現象、業務の流れなど、繰り返しの中で安定性や予測可能性を強調したいときに重宝されます。
たとえば、「例年通り開催される」という言い回しは、「いつも通り問題なく実施される」という安心感を相手に与える効果も持ちます。公式文書や報告書などでも使用される機会が多く、特に行政、教育、ビジネスなどの分野において頻出する言い回しの一つです。
例年通りの例文
「例年通り、4月には会社の新入社員歓迎会が行われ、部署ごとに親睦を深める良い機会となりました。」
「この地域では、例年通り梅雨入りは6月上旬です。農作業の計画もこの時期に合わせて立てられるのが一般的です。」
「例年通り、年末には地域全体で防災訓練が行われる予定です。」
例年通りと毎年の違い
「例年通り」は、単なる「繰り返し」ではなく、過去の傾向や慣習に則って今年も同様に実施されることを意味し、その内容が変わっていないことを強調する表現です。一方で「毎年」は単に「年に一度繰り返される出来事がある」という事実を述べる表現であり、必ずしもその内容が毎回同一であることを保証するものではありません。
たとえば、「毎年イベントがある」と言った場合、その開催方法や内容が毎年異なる可能性もありますが、「例年通りイベントが行われる」と言えば、例年と同じ形式や内容で実施されるというニュアンスが込められています。
例年とは違いについて解説

例年とは違う状況の例
「例年に比べて、今年の桜の開花は早かった。」というように、自然現象に関して過去の傾向と比較する場面でよく使われます。このような使い方は、気候の変動や異常気象といった現象を表現する際にも便利です。
また、「例年と違い、今年の夏は冷夏だった。」という表現は、異なる気候条件を強調する際に用いられ、天候だけでなく、収穫の時期や作物の出来栄えにも影響するため、農業関係者にとっても重要な視点となります。さらに、行事やイベントにおいても、「例年ならこの時期に祭りが開催されるが、今年は中止された」といった文脈で使われることがあります。
例年とは違う場合の使い方
違いを際立たせたいときには、「例年とは異なり」や「例年になく」といった強調表現が効果的です。たとえば、「例年とは異なり、今年は大雪に見舞われた」や「例年になく賑わいを見せた」といった形で、特定の年に特徴的な出来事があったことを際立たせるために使用されます。
また、比較対象があることで読み手や聞き手にとって具体的なイメージが浮かびやすくなり、説得力のある表現になります。文章やレポートで客観的な評価や変化を示す場合にも有効です。
例年とは違いを表現する言葉
「異例」や「通常と異なる」、「例外的」などの語句は、「例年とは違う」という意味を別の形で表現する際に活用できます。これらの表現は、よりフォーマルな文章や、報道・行政文書などでも頻繁に用いられます。
たとえば、「今年の進行は異例の早さだった」や「例外的に暖冬となった」などのように使われ、文章に客観性や専門性を持たせることができます。
毎年の行事との関係
毎年とは何か?
「毎年」とは、年を重ねるごとに継続的に繰り返される出来事や行事を示す表現です。この言葉は、単に時間的な繰り返しを表すものであり、その出来事が定期的に訪れることに焦点が当てられています。具体的には、年賀状を送る習慣や、年末の大掃除、春の花見など、年間を通して同じ時期に繰り返されるような行動や行事が該当します。
また、学校の始業式や卒業式、企業の決算報告など、組織や個人のルーティンとして毎年行われることにも「毎年」という表現が当てはまります。この語は形式や内容の変化にかかわらず、繰り返しがあるという事実を示す際に非常に便利な語句です。
年間の行事と例年の違い
「毎年○○がある」という表現は、その出来事が年に一度必ず起こることを事実として伝えます。一方で「例年○○がある」は、同様の頻度で起きることを指すものの、それが過去の傾向や習慣として続いていることを強調しています。
たとえば、「毎年夏に花火大会が開催される」は、年ごとの継続を表すのに対し、「例年夏には花火大会がある」と言えば、その開催が地域の恒例行事や慣習として定着している印象を与えます。前者は予定・スケジュール寄りの視点、後者は文化や習わしの視点で語られる傾向があります。
毎年に関連する表現
「年中行事」「恒例」「毎年恒例」「定例イベント」「年に一度の催し」などが「毎年」と類似した意味を持つ表現としてよく使われます。これらの語句は、カジュアルな場面からビジネス文書、式典の案内などさまざまな文脈で用いられ、特に「恒例」「毎年恒例」といった表現は、繰り返しによる安心感や期待感を読者・聞き手に与える効果があります。
例年とはの類語と表現方法

例年の類語一覧
「過去の傾向」「これまで通り」「慣例的に」「通常通り」「既定の流れ」「いつもの形式」などが挙げられます。これらの言葉は、過去のパターンや一般的な傾向に基づいた表現として使われることが多く、特に定期的に繰り返される現象や習慣的な出来事の記述において役立ちます。文章や会話のトーンに合わせて、適切な類語を選ぶことで、内容に応じた説得力のある表現が可能になります。
例年を使った言い換え
「いつも通り」「慣例に従って」「定番の形で」「通常の流れで」「例によって」などに言い換えることができます。例えば、「例年行われている行事です」は「いつも通り行われている行事です」や「慣例に従って実施されている行事です」といったように表現を変えることができます。これにより、文脈や受け手の理解度に応じて柔軟な表現を選択できます。
例年に関連する他の言葉
「伝統的」「年中行事」「定例」「慣習」「繰り返しのある」「固定スケジュール」「例年のスケジュール」「時期恒例」などが関係します。これらの言葉は、地域行事や企業活動、学校行事、自然現象などに関して、定期性や繰り返しの意味を強調する際に適しています。文章全体のトーンを統一しながら、より詳細な説明を加えることで、読者に明確なイメージを与えることができます。
例年の使用シーン
例年を使った文例
「例年、この時期は忙しくなります。」という表現は、過去の傾向に基づいて、現在も同様の状況が続いていることを示しています。また、「例年に比べて、今年は来場者数が少なかった。」というように、過去の平均的な状態と今年の状況を比較することで、特異性を際立たせる表現にもなります。
さらに、「例年、年末には大掃除を行います。」や「例年通り、今年も10月に収穫祭が開催されます。」といったように、定期的な行事や活動を表現する際にも頻繁に使用されます。「例年はこの時期に風邪が流行します」などのように、体調管理や生活習慣に関する傾向を伝える文にも使われます。
例年に関連するイベント
例年という言葉が使われるイベントには、学校の入学式・卒業式、運動会や文化祭、地域の盆踊りや秋祭り、年末年始のイルミネーション点灯式、企業の年次総会、株主総会、決算説明会、商品発表会、年末年始セールやキャンペーンなどが含まれます。
これらのイベントは、毎年決まった時期に実施されることで「例年通り」という表現が自然と当てはまります。
例年の概念が使われる業界
「例年」という表現は、さまざまな業界で活用されます。たとえば、気象業界では「例年より早い梅雨入り」などの形で使われ、教育分野では「例年通り夏休みは7月下旬から」といったスケジュールの共有に使われます。
また、観光業界では「例年この時期は紅葉の見頃を迎える」などの季節情報の提供に活用され、農業では「例年通りの作付け計画」として収穫時期や気象に基づいた予測と合わせて使用されます。さらにイベント業界でも「例年の流れに従い準備が進められる」など、年間スケジュールを前提とした行動計画で重要なキーワードとなります。
言葉の違いを理解する

言葉の使い方によるニュアンスの違い
「例年」は、過去の一定期間にわたって継続的に見られる傾向や慣習を示す語であり、その出来事が習慣として根付いていることを表します。一方で「毎年」は、ただ単に年ごとに繰り返されている事実を伝える言葉であり、必ずしもその内容が一貫しているとは限りません。
たとえば、「例年は1月に寒波が訪れる」と言えば、その現象が慣習的・傾向的に起きていることを示しますが、「毎年寒波が来る」と言った場合には、寒波の有無にかかわらず年ごとにあることが前提とされ、多少不正確な印象を与える場合もあります。
例年と毎年の意義
「例年」は、ある一定の期間に観測・経験された傾向に基づく言葉であり、そこには比較・対比・予測といった要素が含まれます。つまり、過去との照らし合わせが前提となっており、「通常どうであったか」という視点を持ちます。
一方、「毎年」は時間的に規則正しい繰り返しを意味し、内容の変化の有無や規模に関係なく、「年に1回必ず起こること」という形式的事実に重きを置いています。この違いを理解することで、文章の信頼性や説得力が大きく変わってきます。
表現の場面に応じた適用
「例年」は、行政文書や報告書、統計分析、ニュース記事など、比較や傾向を前提とした正確性が求められる場面で使用されることが多く、ビジネスや学術的な分野でも頻繁に用いられます。逆に「毎年」は、会話やカジュアルな文書、日常的な表現に適しており、「毎年楽しみにしているイベントです」「毎年の恒例行事です」など、リズムや習慣を軽やかに表現する際に適しています。場面に応じた使い分けを意識することで、文体や伝達内容の整合性を高めることができます。
例年の辞書的定義
辞書での例年の意味
「過去の年と同様な年。また、普通の年。」(出典:広辞苑など)と定義される「例年」は、一定の周期で継続的に起こっている事象や状況を表す言葉として用いられています。この定義は、単に年単位で起きることではなく、習慣性や定型性を持つことを示唆しています。
定義の視点から見る例年
例年という言葉には「通常」「慣例」「恒例」といった意味合いが含まれており、それが特別な出来事ではなく、あくまで「普通」であることがポイントです。この「普通」というのは、過去の実績や経験に基づいて形作られた平均的な状態であり、驚きや新しさよりも安定性や予測可能性を意味しています。そのため、「例年」の語には自然と信頼感や親しみが含まれやすく、読み手や聞き手に安心感を与える効果があります。
辞書を使った例年の解説
各種国語辞典や専門用語辞典においても、「例年」という言葉の定義には一貫した特徴があります。それは、「過去にわたり一定のパターンで繰り返されてきた出来事」「過去数年における慣習的な実績」といった説明がなされている点です。
たとえば、『大辞泉』では「これまでの年と同様な年」と記載されており、『明鏡国語辞典』では「ほぼ毎年繰り返されるような状況をいう」と補足されています。これにより、「例年」という言葉の意味には、単なる回数の多さではなく、そこに確立されたパターンや安定的な流れが含まれていることが明確になります。
例年の学術的な見方

例年の統計的背景
「例年」という言葉は、感覚的・経験的な使い方にとどまらず、統計的な平均や過去の記録データを基にした客観的な判断基準としても頻繁に用いられます。
たとえば、気象庁が発表する「例年の気温」や「例年の降水量」といった情報は、過去数十年にわたる観測データの平均値をもとにしており、それを基準に現年の異常や特異性を判断するのに役立ちます。統計的な背景を持つ「例年」という概念は、科学的、行政的、ビジネス的な分析や報告にも広く応用されており、特にデータドリブンな意思決定において有効な指標のひとつです。
例年を考える上でのポイント
「例年」という言葉を根拠として使う場合、その裏付けとなるデータの範囲や信頼性を十分に考慮する必要があります。たとえば、何年分のデータを採用して平均を出しているのか、その間に極端な事象や例外があったかどうかなどが重要です。
また、データの母数や対象地域、測定方法の一貫性も確認すべきポイントです。特に自然現象や経済動向など、年ごとの変動が大きい分野では、「例年」という表現を用いることでかえって誤解を招く可能性もあるため、注意が求められます。これにより、「例年」という言葉に含まれる比較の前提や信頼度を適切に伝えることができます。
過去との比較から見る例年
ある年が「例年と比べてどうか」という観点で語られるためには、その年が比較の基準となるだけの過去の蓄積と一貫性が必要です。
たとえば、気象観測では30年を一区切りとすることが多く、こうした長期的なデータをもとにしてはじめて「例年通り」「例年に比べて異常」などの表現が成立します。比較の対象として用いるには、統計のばらつきが少なく、かつ定量的に安定したパターンが見られることが理想です。
そのため、「例年」という言葉を使用する際は、単なる慣習表現ではなく、過去との客観的な比較に耐える情報の裏付けを持たせる意識が求められます。
まとめ
「例年」や「例年通り」と「毎年」は、一見すると同じような意味で使われているように見えますが、それぞれに独自のニュアンスや背景があり、細かな使い分けが求められる言葉です。
たとえば、「例年」は過去の傾向や慣習、平均的な状態に基づいており、ある物事が通常どおりに繰り返されていることを強調する際に用いられます。一方で「毎年」は、年ごとに起こる出来事や習慣そのものを指す言葉であり、特に変化の有無や過去との比較には重点が置かれていません。
そのため、「例年」は一定の流れや慣習性を強調するニュアンスを持ち、「毎年」は単なる頻度や周期的な事実を伝える表現となります。このように両者は似て非なるものですが、それぞれの特性を理解し、文章の目的や伝えたい内容に応じて適切に使い分けることで、より的確で説得力のある表現が実現します。
また、ビジネス文書や報道、教育の場面では、「例年」を用いることで過去との比較や分析の文脈が生まれ、より正確で整った情報の伝達につながるでしょう。